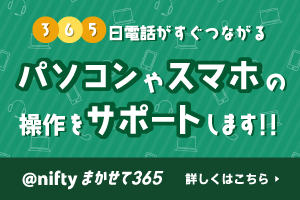Wi-Fi6Eとは?Wi-Fi6との違い メリット・デメリットを解説
2022/11/07テレワークが推奨されるようになり自宅で仕事をする時間が増えると同時に、自宅のインターネットの通信速度を気にする人が増えたのではないでしょうか?
インターネットの通信速度は回線の品質に加え、Wi-Fiの規格でも左右されますが、新しい規格である「Wi-Fi6E」が注目されています。Wi-Fi6Eは2021年に新たに追加された周波数帯規格で、より安定した高速通信が可能になりました。
本記事では、Wi-Fi6Eのメリット・デメリットについて解説します。
パソコンやスマホの設定関連でサポート希望の方はこちら
Wi-Fi6Eとは?
Wi-Fiにはそれぞれ規格があり、これまで規格が更新されるに従い性能も進化してきました。
下記の表を見ると、Wi-Fiは新しい規格ほど通信速度が向上し、利用できる周波数帯が増えていることがわかります。
|
規格 |
策定時期 |
最大通信速度 |
利用できる周波数帯 |
|
|
Wi-Fi6E |
IEEE802.11ax |
2021年2月 |
9.6Gbps |
2.4GHz、5GHz、6GHz |
|
Wi-Fi6 |
IEEE802.11ax |
2019年9月 |
9.6Gbps |
2.4GHz、5GHz |
|
Wi-Fi5 |
IEEE802.11ac |
2013年12月 |
6.9Gbps |
5GHz |
|
Wi-Fi4 |
IEEE802.11n |
2009年9月 |
600Mbps |
2.4GHz、5GHz |
|
IEEE802.11g |
2003年6月 |
54Mbps |
2.4GHz |
|
|
IEEE802.11a |
1999年10月 |
54Mbps |
5GHz |
|
|
IEEE802.11b |
1999年10月 |
11Mbps |
2.4GHz |
|
|
IEEE802.11 |
1997年6月 |
2Mbps |
2.4GHz |
|
Wi-Fi6Eは2021年2月に「Wi-Fi Alliance」によって策定され、2022年9月に総務省が認可した新しい規格です。
Wi-Fi6Eでは新しい周波数帯が利用でき、今まで以上に品質の高い通信が期待できます。
6GHzが利用できることによるメリットは、後ほど「Wi-Fi6との違い」や「Wi-Fi6Eでできること」の項目で詳しく解説します。
Wi-Fi6との違い
Wi-Fi6Eの最大通信速度はWi-Fi6と同じく最大通信速度9.6Gbpsです。
これだけ見るとわざわざWi-Fi6Eを使う必要はないのではと思われますが、利用できる周波数帯が異なります。
Wi-Fi6Eは6GHzの利用が可能
Wi-Fi6で利用できる周波数帯は2.4GHzと5GHzですが、Wi-Fi6Eでは2.4GHzと5GHzに加え、さらに6GHzの周波数帯が利用可能になります。
6GHzの特徴
最初に2.4GHzや5GHzの特長を知ることで、6GHzを利用するメリットが理解できます。
2.4GHzは家電の電磁波と干渉する
2.4GHzは壁や家具があっても電波が届きやすいメリットがあります。
しかし、2.4GHzは家電動作で用いる電磁波として使われているため、近くに電子レンジやテレビなどの家電があると、電波が干渉するデメリットもあります。
5GHzなら干渉しないが利用が多く混線する
2.4GHzのデメリットを踏まえて、5GHzが利用できるWi-Fiの規格が登場しました。
5GHzは他の家電では使われていない帯域なので、近くに電子レンジやテレビがあっても通信が安定します。
その代わりに壁や家具などの障害物には弱いですが、以下のような使い分けが可能になりました。
・他の家電がある場所では5GHzを利用する
・壁や家具によって5GHzが届きにくい場所では2.4GHzを利用する
しかし、現在は5GHzを利用するデバイスが増えたため、複数の端末で同時に利用すると速度が遅くなるデメリットが出てきました。
帯域の幅には限りがあり、5GHzを同時に利用する端末が多くなりすぎると混線してしまいます。
6GHzを使うと混線を避けられる
6GHzが利用可能になると、2.4GHzと5GHzのどちらで通信しても速度が安定しない状態に対処しやすくなります。
例えば近くに家電があり2.4GHzだと電波干渉が起こり、5GHzを利用する端末が多く、どちらを利用しても通信が安定しない状況だとします。
このような状況の場合、もうひとつの選択肢に6GHzがあることで混線を回避した安定した通信が可能となります。
Wi-Fi6Eが登場した理由
Wi-Fi6Eが登場した理由は、2.4GHzや5GHzで生じる混線の解消です。
現在は5GHz対応の端末が増えたため、2.4GHzでの干渉を避けても通信速度が安定しないリスクが生じます。
また家族でネットを利用するパターンが増えたのも、今までのWi-Fi規格で通信が混雑する要因といえるでしょう。
このリスクを解消するためには、もうひとつの道となる周波数帯が必要になるため、6GHzが利用できるWi-F6Eが登場したわけです。
Wi-Fi6Eでできること
Wi-Fi6Eでできることは混雑の回避だけではなく、以下の2つも可能にしました。
・ワイドバンドを利用した高速通信
・低遅延でのゲームプレイ
Wi-Fi6Eで利用できる6GHzは他の帯域よりも道が広いので、混雑の回避だけでなくより高度な通信を実現できます。
ワイドバンドを利用した高速通信
Wi-Fiで用いられる周波数帯はそれぞれでチャネル数が異なります。
チャネル数とはいわゆる車線の数で、多いほど道が広くなります。
2.4GHzで4チャネルと道幅が狭いのに対して、5GHzでは20チャネルと拡大されています。
6GHzでは24チャネルに拡張され、さらに複数チャネルを束ねて道の広さを られるため、6GHzは情報が行き来する道がとても広く、複数の端末で利用しても速度が安定します。
Wi-Fi6でも複数のチャネルを束ねることはできましたが、束ねられる数が少ないデメリットがありました。Wi-Fi6Eでは束ねられるチャネル数が増えたことで、より快適なネット通信ができるようになりました。
低遅延でのゲームプレイ
6GHzのチャネルの多さは、通信速度に加えて遅延を抑える要因にもなります。
送受信するデータの容量が大きくても低遅延で通信できるので、ラグを最小限にしたいオンラインゲームに適しています。
Wi-Fi6Eのメリット
これまで紹介したWi-Fi6Eの特徴を踏まえると、利用するメリットは以下の2つが挙げられます。
・次世代回線の性能を最大限発揮できる
・混雑を回避しやすい
次世代回線の性能を最大限発揮できる
Wi-Fi6Eの大きなメリットは、利用する回線がどのような種類であっても性能を最大限発揮できる点です。
ルーターの規格がWi-Fi6Eであれば、高品質な回線を契約する価値を実感できるでしょう。
混雑を回避しやすい
Wi-Fi6E以前の規格では、回線が優れていても接続する端末の数が多いと混線によって速度が低下するデメリットがありました。
Wi-Fi6Eは帯域幅が広いため、接続するデバイスが多くても混線が起こりにくく通信が安定します。
また先ほどご説明した通り、5GHzの通信が安定しないときに6GHzに接続するといった使い方ができる点も魅力です。
Wi-Fi6Eのデメリット
一方でWi-Fi6Eには以下のデメリットがあるため、利用を検討する際は注意が必要です。
・障害物に弱い
・用途によってはオーバースペック
6GHz帯に対応した機器が必要
Wi-Fi6Eを利用するには、6GHzに対応したWi-Fiルーターとデバイスが必要になります。
ルーターかデバイス片方しか対応していない場合Wi-Fi6Eの利用はできないので、こちらも注意が必要です。
デバイスは最新のハイエンド機であれば、アップデートで対応可能になる場合があるため、対応の可否については直接メーカーに問い合わせてみてください。
利用中のルーターがWi-Fi6E非対応であれば、対応モデルに買い換える必要があります。
※Apple、iPhone 14シリーズでのWi-Fi6E対応は見送られています(2022年10月現在)
障害物に弱い
電波は周波数帯が高くなるほど障害物に弱く、遠くに届きません。
そのため、6GHzを利用する場合はルーターから遠くなると接続できない場合があります。
6GHzは5GHzよりも障害物に弱いので、状況によっては2.4GHzを併用しましょう。
用途によってはオーバースペック
Wi-Fi6Eは安定した無線通信を可能にしますが、インターネットの使い方によってはオーバースペックになる場合があります。
Wi-Fi6E対応ルーターやデバイスを用意するには費用がかかるので、検討する際は利用するネット環境に応じて必要かどうか事前に確認しておきましょう。
以下3つのうち2つ以上に当てはまるのであれば、Wi-Fi6Eは必要ない可能性が高いです。
・Wi-Fiに接続するデバイスの台数が少ない
・オンラインゲームはしない
・動画の視聴はあまりしない
Wi-Fi6Eの設定方法
Wi-Fi6Eを利用する際は設定が必要ですが、基本的な流れは以下の通りです。
1.ONU(回線終端装置)にWi-Fi6E対応ルーターを接続する
2.周波数帯が6GHzのSSIDに接続する
周波数帯が6GHzのSSIDに接続する手順はデバイスごとに若干異なりますが、基本的には以下の通りです。
1.ルーターに付属のラベルを見て6GHzのSSIDと暗号キーを確認
2.デバイス側でWi-Fi接続設定画面を開く
3.①で確認した6GHzのSSIDを選択
4.①で確認した暗号キーを入力
流れだけ見ると簡単ですが、状況によっては対応ルーターの設置後にデバイスから別途設定が必要な場合があります。
またデバイス側での接続設定がわからない人もいるかもしれません。
ニフティが提供するサポートサービス「@nifty まかせて365」では電話窓口はもちろん、遠隔での設定サポートも受けることができるので、加入しておくと安心です。
Wi-Fi6Eを利用する前に、ルーターやデバイスが対応しているかどうかの確認方法を含め、Wi-Fi6E関連の設定に不安な方はぜひご活用ください。
▼@nifty まかせて365の詳細はこちらからご確認ください
※2022年11月時点の情報です。