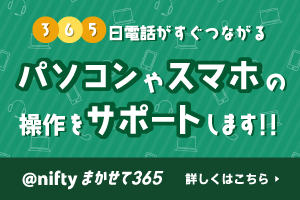画面解像度の「pix」「dpi」「ppi」って何がどう違う?
2020/01/16ディスプレイやスマホ&タブレットの画面解像度に使われる、「pix(ピクセル)」「ppi(ピーピーアイ)」「dpi(ディーピーアイ)」の単位とは? その意味や関係性を理解すれば、電子書籍用タブレット端末を選ぶ基準も見えてくるでしょう。
◆ドンキの電子書籍用・格安タブレットは使えるの?
ドン・キホーテで発売中の、電子書籍向け格安タブレット「電子コミックス 読みまくリーダー」が気になる方は少なくないでしょう。
通常のタブレットやAmazon「Kindle」などと異なり、同製品のディスプレイ・アスペクト比は4:3。コミック単行本や雑誌などの“白銀比”相当で、ディスプレイ・サイズが単行本に近い7.85インチなことから、コミックに特化した端末とも言われます。
アスペクト比&サイズがiPad miniシリーズと同等なことから、一部では廉価版iPad miniとも捉えられているとか。とはいえ、画面解像度:1024×768ピクセル、163ppiというスペックは、あくまで価格相応なもの。電子書籍としては及第点でしょう。
ちなみに、“1024×768”、“2560×1440”などの数値は、画面サイズを表すピクセル数の意味。単位は特にないため数値だけで表記するか、「ピクセル」「pix」などで表します。
ピクセルとは、簡単に説明すると、デジタル画像の最小単位のこと。
デジタル画像は1つ1つの点(ドット)で構成されていて、ドットに色情報をプラスしたものをピクセルと呼びます。
ところが、解像度を表す際にはppiやdpiという単位が使われることも。同じ解像度なのに、pix、ppi、dpiと3つの表記が存在するわけです。
普段からなんとなく目にしている表記ですが、使い分けが難しいことから、混同してしまうケースも多いのでは?
◆スマホやタブレットのディスプレイ性能は「ppi」がポイント
そもそも解像度とは、写真などイメージの密度を数値化したもの。ディスプレイ性能を表す画面解像度も、画面いっぱいに表示させた写真のイメージ密度を基準にしています。
つまり、pix、ppi、dpiとも、数値が高いほど美しく、きめ細かいイメージ(=高解像度)だと考えればいいでしょう。
プリンターやスキャナーのスペックで使われるdpiは、「dots per inch」の略称。1インチ(25.4mm)の1辺に、ドットが何個並んでいるのかを表す単位です。印刷精度など、出力用の単位とも言えます。
dpiとpixは密接な関係にあり、印刷などDTPにおける解像度「dpi」は、1インチ・1辺あたりのピクセル数を意味します。
(例)350dpi=横350pix×縦350pix=122,500pix
ややこしいのは、画面解像度にもピクセルが使われること。そちらは画面上のピクセル数量を表す値で、解像度を示す密度とは概念が異なります。どちらも“解像度”“ピクセル”なので、余計にわかりづらいですね。
一方ppiは、「pixels per inch」の略称。1インチあたりのピクセル(画素)数を表す単位で、「画面解像度」にもよく用いられます。ちなみに、Photoshopの画像解像度も「ppi」で表記されます。
画面サイズが同じならppi数値が高いほど高解像度に。ppiが高い=画面内のドットが小さい=写真や映像が精細に見える……と考えればOKです。
人間の目は、300ppiを境にドットが認識できなくなるといわれます。そのため、300dpi以下のディスプレイではドットが目立ち、粗い画面に感じられるわけです。
前述の「電子コミックス 読みまくリーダー」は163ppi、廉価版「Kindle」も167ppiなので、“それなり”のディスプレイ性能だとわかります。上位機種「Kindle Paperwhite」の300ppiを、タブレット(電子書籍)端末の基準値と考えても良いでしょう。
※2019年12月時点の情報です。