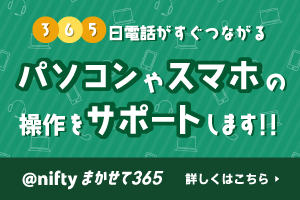ハイバネーション(休止状態)とは?スリープとの違いや無効化のメリット・デメリットを解説
2023/10/19パソコンに備わっている機能「ハイバネーション」。
ハイバネーションは一度パソコンの電源を切った状態にしても、再起動する際に最後の利用状態を復元できる機能です。
一見するとハイバネーションは便利な機能ですが、ストレージへ負担がかかるリスクがあります。
またパソコンを起動する際に立ち上がりが遅くなるため、必要でなければ無効にしておきましょう。
本記事では、パソコンの機能であるハイバネーションについて解説します。
通信速度を改善したい方はこちら
ハイバネーションとは
ハイバネーションとは、パソコンの起動中に一定の使わない時間が経つと、自動で作業状態を保存して電源を落とす機能です。
作業状態とは、デスクトップ上で開いているアプリやファイルを開いている状況を指します。
パソコンの起動中は、メモリに作業状態が保存されますが、ハイバネーションが機能すると、メモリ上で展開していた作業状態がSSDやHDDなどのストレージに保存されるので、メモリには何も保存されません。
そして、再度パソコンを起動すると自動で最後の作業状態が復元されます。
ちなみに、WindowsではVista以降のバージョンでは、標準でハイバネーションが機能する設定になっています。
ハイバネーションを利用するリスク
ハイバネーションは作業状態を保存できる便利な機能ですが、利用には以下のデメリットがあります。
・SSDやHDDへ負担がかかる
・再度起動する際の立ち上がりに時間がかかる
SSDやHD へ負担がかかる
ハイバネーションを利用する場合、電源を切るときに作業状態が内蔵のSSDやHDDへ保存されます。
そして、再度パソコンを起動する際は、SSDや HDDから保存している作業状態を読み込まなければいけません。
作業状態の保存ファイルは、内蔵メモリのスペックによって異なり、作業状態ファイルの容量は内蔵メモリの75%です。
メモリの容量別にまとめると、内蔵ストレージへ以下の容量を書き込み、そして読み込みます。
|
メモリ容量 |
書き込み・読み込みの容量 |
|
4GB |
3GB |
|
8GB |
6GB |
|
16GB |
12GB |
|
32GB |
24GB |
ハイバネーションを頻繁に利用すると、毎回内蔵ストレージに上記の容量で負荷をかけ、寿命の短縮に繋がる恐れがあります。
また、読み書き回数を消費するほどSSDやHDDの寿命は近くなるので、ハイバネーションの頻繁な利用はおすすめしにくいです。
内蔵ストレージの寿命が近づくと、パソコンの処理速度が遅くなる要因にもなるので注意が必要です。
PCの処理速度に影響するSSDの寿命は何年?寿命が近い時の対処法を解説
再度起動する際の立ち上がりに時間がかかる
ハイバネーションを利用してパソコンを再起動する場合、GB規模でファイルを読み込んで作業状態を復旧しなければいけません。
そのため、通常の状態でパソコンを起動するよりも立ち上がりに時間がかかり、スムーズに作業を再開できるとは言いがたいです。
ハイバネーションとスリープの違い
ハイバネーションとスリープは、どちらもパソコンを一定時間利用していないと作動する機能です。
しかし、以下の2点に違いがあり根本的な目的は異なります。
・データを保存するパーツ
・電源が落ちるか
上記の違いがあるため、状況によってはスリープの利用がおすすめになります。
スリープでのデータ保存先はメモリ
ハイバネーションは、パソコンが休止状態になり電源が落ちると作業中のデータがSSDやHDDに保存されます。
スリープでは、作業している状態のデータの保存先がメモリになるため、スリープを利用すると内蔵ストレージに負荷がかかりません。
スリープでは電源が落ちない
ハイバネーションでは、電源を落としても起動したら元の作業状態が復元されますが、スリープではパソコンの画面だけ落とし、作業状態をメモリに保存した状態で電源が付いた状態が維持されます。
そのため、スリープ状態から復帰する場合、ハイバネーションよりも早く作業状態を復帰でき、パソコンの立ち上がり完了を待つ必要もありません。
ハイバネーションを無効化するメリット
できる限りパソコンを長く使いたい場合、ハイバネーションの無効化は寿命を長くする方法の1つといえます。
先ほどまでの内容を踏まえると、ハイバネーションの無効化には以下2つのメリットがあるためです。
・SSD・HDDへの負担が減る
・作業状態復元が早くなる
SSD・HDDへの負担が減る
ハイバネーションを利用すると、電源落ちや再起動の度にGB単位の保存や読み込みを行うため、ハイバネーションが機能する度に、内蔵ストレージに負荷がかかることになります。
ハイバネーションを無効化することで、GB単位での負荷を内蔵ストレージにかけず寿命を長くすることができます。
作業状態復元が早くなる
ハイバネーションを無効化すると、内蔵ストレージから作業状態ファイルを読み込む必要がありません。
そのため、作業に戻る際の状態復元がスムーズに行えます。
ハイバネーションを無効化するデメリット
ハイバネーションの無効化には、以下2つのデメリットもあります。
・意図せずパソコンの電源が落ちると作業状態が消える
・電力消費が増える
そのため、状況によっては無効化しないのも選択肢です。
意図せずパソコンの電源が落ちると作業状態が消える
ハイバネーションを無効にする場合、特に注意したいのは予期せぬパソコンの電源落ちです。
デスクトップパソコンでは、停電で電源が切れると作業状態が消え、ノートパソコンでは、充電切れによって電源が切れて作業状態が消失する恐れがあり要注意です。
ハイバネーションを無効にするのであれば、以上のリスクに注意したうえでパソコンを使用しましょう。
電力消費が増える
ハイバネーションを無効化すると、どれだけパソコンを放置しても電源は落ちないため、パソコンから離れる時間が長くなりがちだと、かえって電力消費が増えてしまいます。
パソコンから長時間離れる場面が多いのであれば、ハイバネーションを有効にするか、離席する度にパソコンの電源を落としましょう。
SSD・HDDの寿命を延ばすためには無効化
SSD・HDDの寿命を延ばしたいのであれば、ハイバネーションは無効化しておきましょう。
無効化する手順は簡単です。
まず以下の手順でコマンドプロンプトを起動します。
1.WindowsキーとXキーを同時に押す
2.「コマンドプロンプト(管理者)」を左クリック
コマンドプロンプトが起動したら、以下の手順を行なってください。
1.ウィンドウの末尾で「powercfg /h off」と入力
2.Enterキーを押す
3.ウィンドウの末尾で「exit」と入力
4.Enterキーを押す
以上でハイバネーションの無効化は完了です。
通信速度も改善したいなら光回線の乗り換え
パソコンを再起動するときの立ち上がり、処理速度を意識している人は、特にネットの通信環境は気になるところです。
通信環境を改善したいと思った場合、まず周辺機器や周辺環境の見直しが対処法に挙げられますが、回線の見直しは効果的な方法です。
回線の品質はプロバイダーによって違うため、契約先を変えるだけでも通信環境が改善する可能性があります
おすすめは「@nifty光」です。
@nifty光では、IPv6接続の利用によって混雑しない経路を通っての通信が行えます。
光回線の通信速度はIPv6接続の対応有無で変わるので、一度検討してみてはいかがでしょうか?
※2023年10月時点の情報です
IPv6の利用状況を確認する2つの方法|スマホやタブレットでもチェックしよう