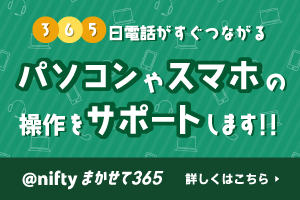BYODとは?オンライン授業に最適なパソコンの選び方と通信環境
2020/09/23コロナ禍によって学校や塾などで、オンライン授業の整備が急ピッチで整えられるようになり、多くの教育機関で学生が所持しているパソコンやタブレットを活用するBYODが採用されています。
今回は今後さらに推進されていくであろうBYODについて、おすすめのパソコンの選び方からオンライン授業を快適に受ける方法まで解説していきます。
教育機関でも推進されているBYODの導入
近頃大学や塾などで積極的に採用されているBYODとは何なのでしょうか。BYODのメリット・デメリットについて解説します。
BYODとは
BYODとは、Bring your own deviceの頭文字で「個人が保有しているパソコンなどの端末を活用すること」です。
普段使用しているパソコンなどの端末を学内ネットワークに接続することで、オンライン授業や履修登録などが利用できます。
「BYOD(ビーワイオーディ)」とは-意外と知らないIT用語の基本
BYODのメリット・デメリット
BYODの目的は、個人のパソコンを活用して情報通信技術(ICT)を利活用することです。個人のパソコンを使ってどこでも学習ができ、履修登録や各種配布をデータで受け取ることができるというメリットがあります。
しかし、個人が保有しているパソコンのため、情報セキュリティリスクが高まるといったデメリットが生じる可能性もあります。
ここで、BYODのメリット・デメリットについて確認しておきましょう。

BYODの採用は教育機関と学生双方にメリットが大きく、特にオンライン授業の需要は高まっており、教育機関はBYODによって浮いたコストで、通信環境やソフトウエアの取得・提供などにコストをかけることができます。
しかし、個人が保有している端末を活用するため、端末のスペック差や通信環境による生徒間の利便性に差がでてしまう懸念があります。
BYODを推進する上で、教育機関は生徒が活用するさまざまな種類の端末に対応できるように環境を整えなくてはなりません。
そのため一部の教育機関ではBYAD(Bring your assigned device)を採用し、活用端末を指定し、端末による性能差が出ないよう制限を行っているところもあります。
導入されているオンライン授業の種類
BYODが導入されている教育機関では、オンライン授業の整備が行われています。
オンライン授業は、自宅でも教室と同じような授業を受けることができるため、注目が集まっている授業スタイルです。
オンライン授業の種類は大きくわけてリアルタイムで配信を行う授業と配信された動画を視聴するオンデマンド授業の2種類があります。
それぞれの授業の特徴について確認しておきましょう。
教室で受けているような授業が魅力の「リアルタイム配信授業」
リアルタイム配信授業は、決まった時間に講師がZoomやSkypeなどを利用し授業を行うスタイルです。
リアルタイム配信授業の主な特徴は以下の通りです。
[メリット]
・自宅にいながら今までと同じような授業が受けられる。
・その場で質問や意見交換ができるため、班に分かれて行う授業や発表会もスムーズに行うことができる。
[デメリット]
・パソコンやWEBカメラ、マイクなど、オンライン授業を受けるために機器の購入が必要になる場合もある。
・映像と音声を送受信するため、安定した通信環境と高いスペックのパソコンが必要。
リアルタイム配信授業は、今までと同じ様な雰囲気で授業が受けられることが一番の魅力ですが、生徒が参加する環境によって、映像や音声が途切れてしまうというトラブルがおきてしまう可能性があります。
学生のペースで学習できる「オンデマンド授業」
オンデマンド授業は、あらかじめ録画された動画を視聴するもので、いつでも授業が受けられる自由度の高い授業スタイルです。
オンデマンド授業の主な特徴は以下の通りです。
[メリット]
・生徒はいつでも好きな時に好きな場所で学習ができる。
・動画の視聴だけなのでリアルタイム配信授業よりもデータ通信量を抑えることができる。
[デメリット]
・生徒自身による自己管理が必要なため、場合によっては生徒間で履修状況に差ができてしまう。
・動画を視聴して授業を受けるため、通常の授業とは異なり質問や意見交換がしづらい。
オンデマンド授業はあらかじめ録画された授業動画を視聴することで、生徒はいつでも好きな時に学習できることが特徴ですが、一方で生徒自身が自己管理をしっかり行わなければならず、怠けてしまうと生徒間で履修状況に差がついてしまいます。
オンライン授業を受けるために欠かせない環境づくり

オンライン授業を受けるためには、授業を受ける環境づくりをしなければなりません。
ここではオンライン授業を受けるために必要なパソコン、タブレットの選び方についてご紹介します。
使用する端末や必要なスペックは?
オンライン授業を受けるためには、まずパソコンやタブレットといった端末を用意しなければなりません。パソコンやタブレットにはスペックによって価格が異なり、必要なスペックによって選び方が変わってきます。
BYODを推進している慶應義塾大学の推奨ノートパソコンスペックを参考に、表にまとめてみました。

基本的には、オンライン授業を受けたい教育機関で推奨されているスペックのノートパソコンを用意することをおすすめします。
最近ではタブレットもスペックが高くなっているため、タブレットで気軽に授業を受ける人も増えているでしょう。
他にも、持ち運びがしやすいよう、鞄に入りやすいサイズや重さの製品を選ぶことも大切です。
またパソコンとタブレット、使用する端末によってメリット・デメリットがあるので参考にしてみてください。
【パソコンで授業を受ける時の特徴・メリット・デメリット】
【タブレットで授業を受ける時の特徴・メリット・デメリット】
通信環境によって快適度が異なる
快適なオンライン授業を受けるためには、パソコンのスペックと合わせて通信環境も重要になってきます。通信環境が悪いと動画が止まってしまったり、音声が途切れてしまったりとスムーズに授業を受けることができません。
特にリアルタイム配信授業では映像と音声を送受信するため、通信環境によって受講に影響が出てしまう可能性があります。
こちらの表は主なWEB会議ツールでオンライン授業を受けた場合の参考通信量です。
授業の受け方や利用するツールによって通信量が異なります。受ける授業が多ければ消費通信量は多くなるため、モバイル通信では速度制限や高額な通信料が発生してしまう場合もあります。
リアルタイム配信授業も快適に受けられる光回線
オンライン授業は多くのデータ通信を行うため、モバイル通信ではすぐに速度制限になってしまいます。また、通信環境が不安定だと動画のカクつきや画面の荒れ、音声が途切れてしまうといったトラブルも考えられます。
快適なオンライン授業を受けるために安定した通信環境を整えたい方は、光回線がおすすめです。
光回線はモバイル通信と異なり、データ通信量に制限がないため速度制限になる心配がありません。また回線が安定しているので、動画が止まるかもしれない、といったストレスなく授業を受けることができるでしょう。
光回線はたくさんのサービスが提供されていますが、中でも「@nifty光」がおすすめです。
全国でサービス提供されていて、最大1Gbpsの高速通信が可能なため、解像度の高い動画もスムーズに視聴ができます。さらに、通信量が地域や時間帯に影響されることが少ない「IPv6」接続に対応しているので、授業を受ける時も安心です。
IPv6とは|接続確認から申込まで初心者にもわかりやすく解説
BYODを導入する教育機関は今後さらに増えていく可能性が高いため、できるだけ早めに環境を整える必要があります。
自分にあったパソコンなどの端末を選ぶことはもちろん、快適な通信環境も「@nifty光」で整えてみてはいかがでしょうか。
※2020年9月時点の情報です。
※本文中に記載されている通信速度は理論値です。必ずしもこの速度が保証されているものではなく、お客様の通信環境や接続の時間帯などによっては、思うように速度が出ない場合や接続が不安定な場合があります。